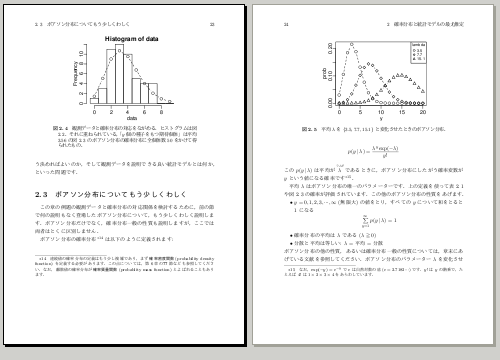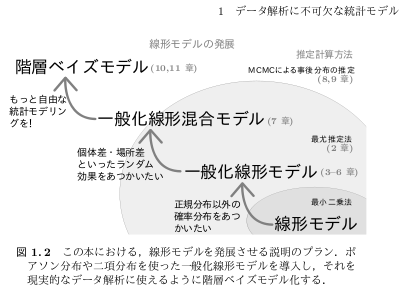
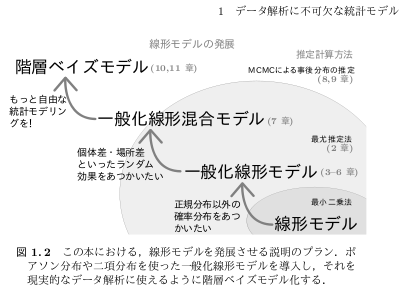

see
はヘンなバグがあるな.
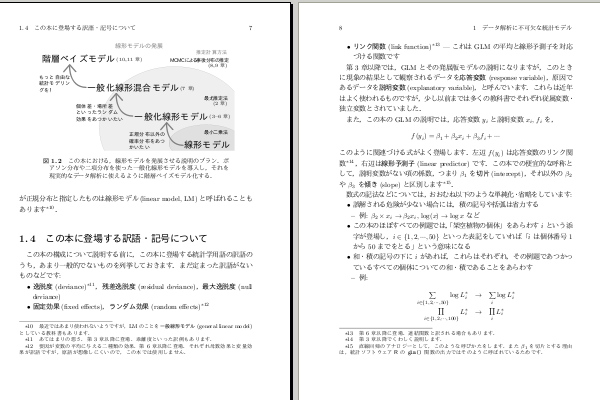
\index{}
のマクロを工夫したので,
索引項目だけは増殖中
……
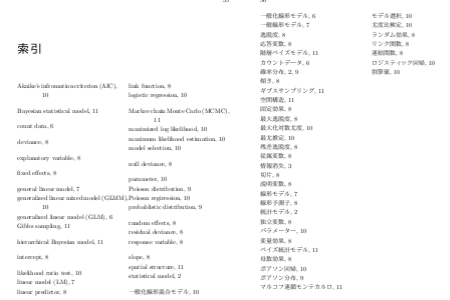
glm()
ではあるんだが.
library(lme4)
の
lmer()
関数なんぞを使わねばならんことに.
いやはや.
速度差なので
... + (time | id) + ...
か
……
いやいや,
速度差だけに個体差があるので
lmer()
のばかっぽい記法で
... + (0 + time | id) + ...
だな.
lmer()
の「このデータでは個体差と測定誤差の区別できねーよ,
でなおしてこい」
警告 & 計算拒否攻撃をくらう
……
さてさて,
いつもはここで「ばかばかしいから lmer() なんぞやーめた」
「こんなのもうゐんばぐす + 重量測定器の測定誤差についての『主観的』
事前分布でケリをつけちまえ!」
戦術にさっさと移行するのだが
……
lmer()
に対する復讐心のみに駆動されて,
ここで上記計算拒否攻撃を突破するワザの天啓を得た.
まことにばかばかしい方式で,
観測データがデータフレイム
d
に入っていたとすると,
これを
dd <- rbind(d, d)
といった塩梅で「複写によるデータ倍増」,
あたかも「一個体から 2 つずつデータを得た」
ように見せかけると,
lmer()
はバカだからだまされて推定計算やってくれるんだよね
(しかもテストデータで確認すると,
わりと正確に個体差のばらつきを推定した).
lmer()
幻惑データ重複わざ
……
まあ,
独創的な呪術ですかね.
小役人の巧妙なウラ金づくりみたいなものかな?
lmer()
遊びもここまでで,
データをよくよく見ると
なぜかというと非線形混合効果モデルが必要であり
(理由は対象の崩壊速度が一定ではなく,
時間とともに速度低下するため)
lmer()
ではなくその非線形版たる
nlmer()
が必要,
でこいつを動かすためには
R 呪われわざのひとつ
selfStart クラスの定義,
すなわち self-starting 非線形クラスの定義を書かねばならず,
これは
4 年前にも何やら苦闘
してたのだけど,
すごーくめんどう & 難解なのでヤメ.

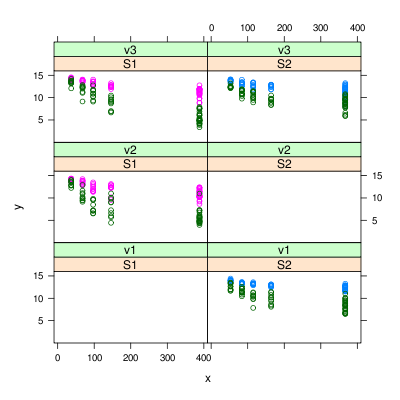
不審者の出没による注意喚起について
このことについて、総務部総務課から別添のとおり連絡がありました
ので、お知らせいたします。
昨日(8/25)、午前1時頃、獣医学研究科附属動物病院付近に
タオルで覆面をした不審者がいたとの通報がありました。
つきましては、夜道の一人歩きや街灯のない暗がり等の通行は極力
避けるよう心がけてください。
不審者の出没による注意喚起について
このことについて、総務部総務課から別添のとおり連絡がありました
ので、お知らせいたします。
昨日(8/25)、午前1時頃、獣医学研究科附属動物病院付近に
タオルで覆面をした不審者がいたとの通報がありました。
つきましては、夜道の一人歩きや街灯のない暗がり等の通行は極力
避けるよう心がけてください。
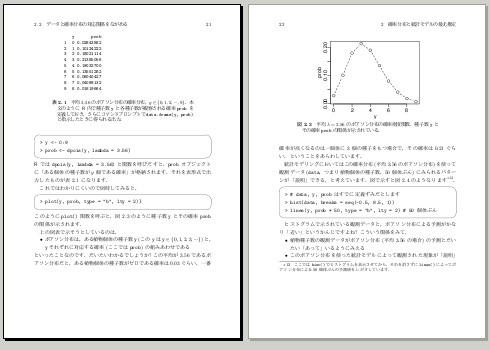
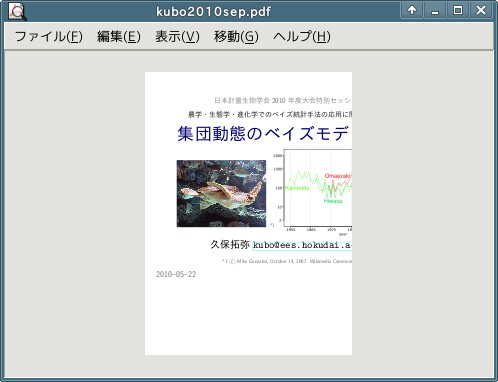
\documentclass{seminar}
のせい.
5 年ほど前
にもこのあたり苦闘させられたのだが
……
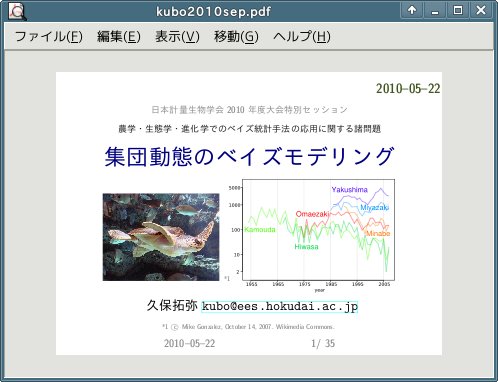
seminar.con
の新旧
diff
はやった本人が見てもまったく不合理としか思えないモノである
……
$ diff seminarOLD.tex seminar.tex
7,9c7,8
< % A4 横長
< \setlength\paperheight{287mm}
< \setlength\paperwidth{210mm}
---
> \setlength\paperwidth{300mm}
> \setlength\paperheight{220mm}
13,16c12,16
< \setlength{\slidewidth}{0.94\paperheight} % height -> width
< \setlength{\slideheight}{0.85\paperwidth} % width -> height
< \def\slideleftmargin{0.04\paperheight}
< \def\sliderightmargin{0.02\paperheight}
---
> \setlength{\slidewidth}{0.99\paperwidth}
> \setlength{\slideheight}{0.90\paperheight}
> \def\slideleftmargin{0.28\paperwidth}
> \def\slidebottommargin{0.42\paperheight}
> \def\sliderightmargin{0.01\paperwidth}
18d17
< \def\slidebottommargin{0.03\paperheight}
52c51
< \setlength{\Swidth}{0.40\paperwidth} % ????
---
> \setlength{\Swidth}{0.30\slidewidth} % ????
\documentclass{seminar}
は卒業すべきかなぁ
……
しかしこのあたり強化する時間的・精神的よゆーが欠落している日々.

早速ですが、学術助成あてご質問のありました 標記の件、現状ではまったくもって「未定」であり ます。 いずれ、学務部のほうから監督員の派遣依頼 (この時点で人数が指定されます)があり、部門 毎に「○人出してください・・・」という依頼文書を 総務から出しているようです。 詳細は、それ以降にならないと分からないので、 何卒ご了承下さい。
今日はちょっと札幌大会の口頭発表申し込みについての,技術的な問題につい てのご意見いただければ,といった理由でメイルさしあげています.そんなに 急ぎの件ではないと思いますので,お時間あるときにでもご意見いただけると 助かります. 口頭発表編成作業を少しラクにするため,申し込み時に「この発表分野の残り 『わく』数はいくつ」といった表示があったらよいのでは,と考えています. 口頭発表編成では, (1) 第一希望の申し込み数が少なすぎる発表分野は廃止→第二希望へ (2) 第一希望の申し込み数が多すぎる発表分野では,一部の人だけ第二希望へ といった第二希望分野への移転をします.(1) はいかんともしがたいのですが, (2) に関しては残りわく数みたいなものを表示して,それがゼロになればもう しこみできなくなる,といった…… と, ここまで書いたところで, 「あ,もうめんどくさくなったから 先着順 でいいじゃん!」 という着想にもとづく解決策の一案を得た.